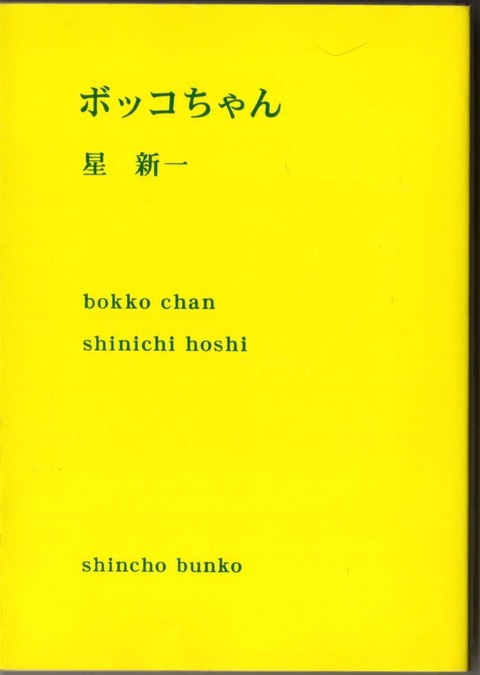新潮社作品集「ボッコちゃん」と講談社の「エヌ氏の遊園地」に掲載されている「殺し屋ですのよ」について書いてみようと思います。
作品集「ボッコちゃん」は何冊持っているだろうか。
黄色の表紙は何の記念だったか。
新潮社では、文庫本の○○刷記念や夏の○○フェアーなどの際に、黄色や緑色の表紙に着飾った文庫本を発売しています。
新たな印刷ほど技術が向上し、読みやすいので、本屋さんで目にするとつい買ってしまう癖が僕にはあります。
中編、長編小説なら一度読んでしまえば、本棚にしまい込んで再び読むことはめったにないのですが、ショートショートは何度も読み返し、そのたび新たな読後感に浸れるという良さがあります。
「エヌ氏の遊園地」には、巻末に「解説風あとがき」と題して自己の作風について書いています。
解説無用論者であり、更にあとがき無用論者としても有名な氏が「解説風あとがき」を書いている。
そして短編集「宇宙のあいさつ」には「あとがき」と題した短編を掲載しています。
「解説を必要とするほどの難解な作品は、ほとんど書いていないつもりである。そもそも、作家は作品を通じて理解するものであると考えており、解説無用論者である」
と言いながら
「自分が誰かの本を読み終えた時、あとがきや解説がないと何となく物足りなさを感じる。私の内心に解説への需要があることは確かだ。まったく矛盾もいいところ」
という反対の自分がいることも認めています。
作品についてですが「殺し屋ですのよ」のタイトルがまず、秀逸です。
星新一の作品は異質なもの同士の組み合わせから新たな物語が動き出します。
主人公の女性は、若く上品で、殺し屋という職業とは大きなギャップがあります。
そして、対象者を殺しに向かうのではなく、商売敵を殺してあげます。と殺人の御用聞きにくるという話の展開はこれまた人を食った星新一らしい作品です。
殺し屋が「ですのよ」なんてどうみても不釣り合いな物語の序盤から、あっと驚く結末へ。
ショートショートの作品紹介は難しい。内容に触れればネタバレになるし、じゃ、何を書けばよいのか。
でも、巧いよな。無駄がない。
これが他の作家の作品と星新一作品の大きな違いです。スマートにサラリとした作品はなかなか真似できない。
初期の星作品は、最後の「オチ」、どんでん返しが素晴らしいと評価されています。
星新一本人も「オチ」という言葉を使いますが、僕にはこの「オチ」という言葉では、コント的な、お笑い的な印象があり、もっと文学作品に相応しい名称はないものかと常々感じています。
そのあたりも、星新一作品の評価にとってマイナスなのではないだろうか。
僕たちは「大作で深刻で難解」な作品を文学作品と評価し「短く軽く読みやすい」作品を低く評価しがちです。
星作品に接した多くの読者が、子供向けだと思っているようですが、小学生から大人まで世代を問わず作品を手にすることができ、その世代世代で読後感が変わり、深く心に触れてくる作品は、音楽、絵画などの優れた芸術作品に共通する特徴です。
星新一作品は、ほぼすべて手に入れました。
あとは、一作一作を楽しみながら新たな発見をすることが、僕の残された人生の楽しみのひとつ。
でも、残りの時間では読み切れそうにない膨大な作品群が……