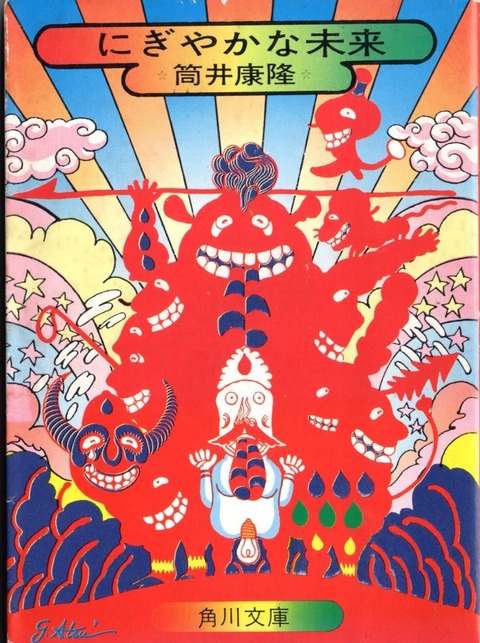「にぎやかな未来」は最初、三一書房から豪華本で出版されました。
1968年(昭和43年)初版
(三一書房版)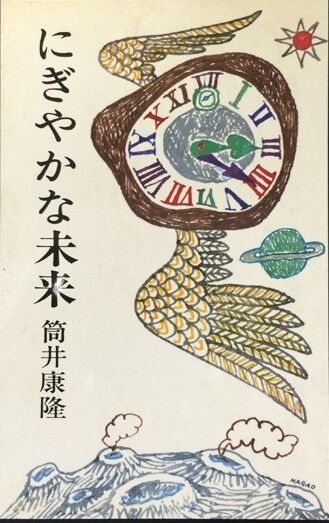
これがその本の表紙ですが、勿論、手元にはありません。
手元にあるのはこちらです。
↓
1976年(昭和51年)初版(徳間書店版)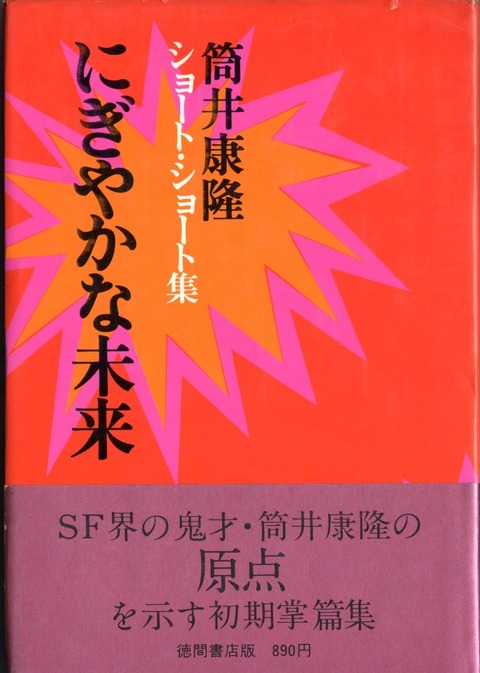
この単行本はネットで手に入れたもので、最初は、文庫本で読みました。あの頃は、星新一以外は文庫本で、気に入ったら単行本を探して所蔵するという感じでした。
今はネットで見つかるので良い時代になりました。
この本にはデビュー作の「お助け」と、断筆宣言のきっかけになったあの「無人警察」が掲載されています。
” 最初、それは細君との口論からはじまった。妙にノロノロしたいい方で彼女は彼に、数日来の不満をぶちまけたのである”
で始まる「お助け」
文字数制限のある超短編は、無駄な言葉は極力削り物語を始めなければならない。さすが筒井先生。
主人公の男は、宇宙飛行士の訓練のためか、周囲の時間が異常に遅く進むように感じるほど、自分の身体能力や感性までもが、社会生活が営めないほど速くなってしまった。
そんな男の話です。
他人との時間の速度のズレが大きくなり、誰とも交流ができない虚無感。
彼の目には止まっているとしか見えない人たちに、思いつく限りのイタヅラをしても、その反応を見ることができない。
そして、これでもかと言うほど残酷な結末が待っています。
先ほどの徳間書店で単行本を刊行する前に、角川文庫から文庫本が刊行されています。
発行元が異なるとはいえ、単行本が文庫本より後から刊行されるのを僕は初めてみました。
何故だろう。
文庫本の「あとがき」は星新一が書いています。
「お助け」について、「この幕切れははなはだしく残酷である。だれにも気づかれることのない一瞬という時間のなかで、じわじわと救いのない死におちいっていく…「お助け」には純粋な残酷がある。無色透明な残酷である。」
筒井康隆が描く残酷に対する分析です。
星新一の超短編集に慣れ親しんでいた僕にとって、筒井康隆の作品は異質でした。
星新一の作品は上品で上質、個人の個性はあまりなく、いつの時代なのか。僕にとって読後感は静かで、次の作品に読み進んでしまいます。
そして、徐々に染み込んできます。
比較すると筒井康隆の登場人物は、もっと個性的で、人間の欲望が露わで、こんな奴いないよと思いつつも、その物語に引き込まれてしまう。時に抱腹絶倒、時に嫌悪感、人間の毒が作品から飛び散ります。
つまりパンチ力がある。
それが筒井作品です。