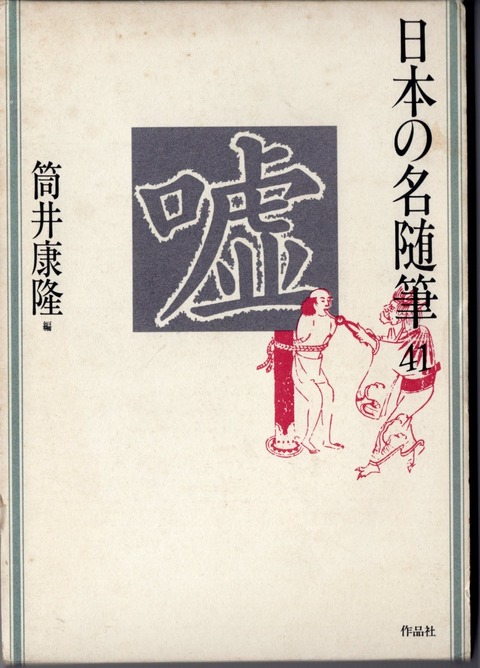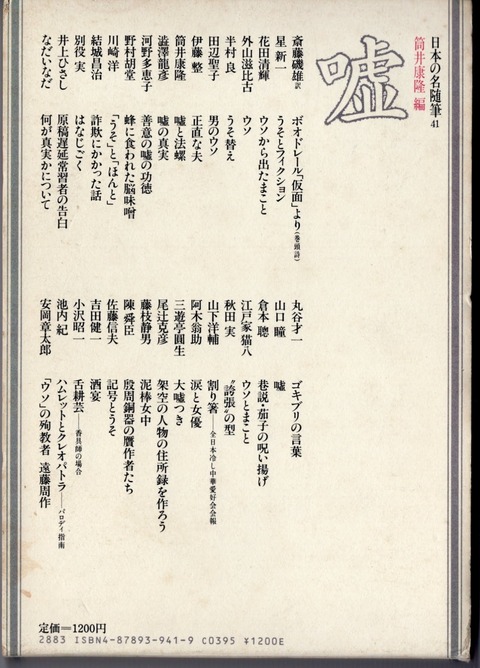日本の名随筆シリーズ(筒井康隆編)
『嘘と法螺』筒井康隆
“靴を片方なくして帰ってきた子“
親:靴はどうした?
子:泥棒が持って逃げた
親:警察に言わなかったのか?
子:盗んだのは警官だ
親:片方だけ盗んでも役に立たないだろう?
子:警官は片足だった
親に叱られない為に嘘を重ねて、最後には「非現実的な話」になってきた。
このような嘘から「叱られないため」という目的がなくなれば、そこには芸術的価値が生じる。(要約)
嘘→デタラメ→法螺話→物語
誰も物語(小説)を嘘だといって怒る人はいない。
…文学雑誌の座談会で「これは驚いた。文学が空想を否定するものとは思わなかったぞ」と星新一が発言をしていたこともある。
日本の文壇には、星新一氏が驚くような、この種の本末転倒の頓珍漢があるので僕は嫌いだ。
嘘であることが最初からわかっているジャンル、つまりSFを選んだのはそのためかも知れない。
(筒井)
『うそとフィクション』星新一
東京タワーのそばの高層アパートに住んでいたころの話。
来客に「こんなに近いと電波が強くて、寝ていてもコマーシャルの夢を見るんですよ」
すると時々「そうでしょうね」と感心し、本気で信じる人がいる。
これには冷や汗をかいたといいます。
フィクションの楽しさが成立するには、
①相手が正気でなければならない
②無知であってはならない
③健全な常識の持ち主でなければならない
(星)
フィクションではアメリカが進んでいる。小説を読むとよくわかる。
アメリカ人は日常ではフィクションを好むが、法廷で宣誓し証人となると、ほとんど嘘をつかない。
これに反し、わが国では証言はあまり重要視されない。ウソとフィクションのけじめがないのだ。(星)
編者あとがき
「純文学作家の書いた随筆にはおもしろい物が少ない。
難しくておもしろくないというのではない。随筆を見くびっているのだ」
エンターテイメントの作家の随筆はたいていおもしろい。筋金入りにおもしろい。
(筒井)