SFの始まりは…
SFの起源はどこにあるのか。これに対する答えは、他の小説などの文学の起源と同じく、人類が文字によるコミュニケーション手段を手に入れたと同時期、つまり数千年前に遡り「原小説」「原SF」があったのだと想像します。
例えば、記録として確認できるのは、古代ギリシャ、古代支那地方に残る神話であり、我が国においては、古事記、日本書紀に繰り広げられた物語、さらには、この記紀の原型とされる「帝記」「旧辞」にまで遡り、時代は下り「竹取物語」や「日本霊異記」などの説話文学など、日本文学も世界に引けを取らずSF的文学作品がたくさんあります。
物語という定義をもっと広く緩めれば、文字を手に入れる以前の人類にあっては、例えば縄文人たちが、今でいう「文学的才のある」誰かが、夜な夜な思いつくままに「縄文酒」を酌み交わしながら作り話を話しみんなを喜ばしていたのではないか。
ここまで遡れば、もうこれは想像の域をでないのですが、とても夢のある仮説ではないだろうか。
SFの起源を古代にまで遡り論じることはこの程度にして、近代文学史的に言えば、十九世紀のイギリスの作家、メアリー・シェリーが1818年に「フランケンシュタイン」を、フランスのジュール・ヴェルヌが1869年「海底二万里」を、イギリスのH・G・ウェルズは1895年に「タイムマシン」を発表していて、この時代が近代的なSF文学の起源といわれています。
SF小説の定義としては「科学的知識を基にした幻想的な設定で未来の世界を描く小説」などと説明され、サイエンス・フィクションとも呼ばれましたが、現代ではSF小説という名称が定着しています。
当時の科学的知識を基に、宇宙からの侵略者、未来からの訪問者、地底深くに築かれた文明などを題材とした物語が初期SFとして書かれました。
H・G・ウェルズの「宇宙戦争」は、「火星人襲来」というタイトルでラジオドラマとして流され「宇宙船の中から火星人が現れ、ニュージャージー州の田舎の住民40人が殺害されたされた…」というその生々しい放送に、住民がパニックになったというエピソードが有名ですが、このようにしてSF小説は徐々に世界に広がっていきました。


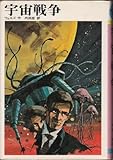
SFの定義とは
SFの定義とは、狭義的には「科学的知識を基にした幻想的な設定で未来の世界を描く小説」であると書きましたが、新たな文学、SF小説が世界に拡散し、時代が経つにつれ、才能ある作家たちは様々な形式、様々なアイデアの作品が上梓され続けました。
それは、地域性や国民性、時代性の違いもあり、「SとF」それ自体の定義も多様化し、
「サイエンス・フィクション」…科学小説
「サイエンス・ファンタジー」…幻想小説
「スペキュレイティヴ・フィクション」
…思弁小説
「スペキュレイティヴ・フェビュレーション」
…思弁的寓話
「サイエンス」自体の意味も、自然科学の意味から、社会科学分野に広がり、政治、経済、国際、習慣、哲学等々取り扱う世界は無限に広がり出しました。
宇宙を舞台、未来社会、異星人の侵略、異星人とのコンタクト、他の動物の襲来、タイムマシーン、タイムスリップ、タイムパラドックス、多次元宇宙、ミクロの世界、超能力、ロボット、突然変異生物、世界の終末、人類絶滅、スラップスティック、精神世界、宗教、原始社会等々、その取り扱う題材や文学的手法はさらに漫画や音楽、イラストレーションなどの美術の世界までも包み込み、その裾野は今なお広がり続けています。
日本SFの始祖は…
日本では、海野十三というSFの先駆者がいました。
大正から昭和初期、まだその当時のSFは変格探偵小説として「科学小説」と呼ばれ、探偵小説や推理小説の一変異体的な扱いで、この「科学小説」という名称は、日本近代SFの昭和初期当時の呼び方で昭和30年代まで使われました。
名前の読みは「うんの じゅうざ」
本名 佐野昌一
明治30年生、昭和24年没 享年52歳
逓信省電気試験所勤務
推理作家、空想科学小説家、漫画家、科学者
デビュー作 「電気風呂の怪死事件」
代表作 「蝿男」「火星兵団」「火葬国風景」「深夜の市長」「太平洋魔城」
海野十三が空想科学小説を執筆したのは、戦後、日本のSFが本格的に活動し始める30年も前のことです。
アメリカと日本のSFの決定的な違いは、リビングにテレビが有るかないかの違いだ。と誰かが書いていました。SFの描写風景には確かに大きな存在です。
近未来を描く際、家電、自動車、電話機などが風景に写し込まれない作品は、現代の僕たちからすればどこか不自然です。
その意味でも、高度成長期に始まった日本SFは、正に「時宜を得た」と言えるのではないだろうか。
残念ながら、海野十三氏のSFは、今となっては古めかしい。やはり早すぎた才能だったのかも知れません。
しかしこれだけはいえます。今のSFの興隆は、海野十三たち先駆者の努力があってのことです。
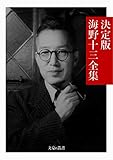

本格的SFの始まりは…
そして戦後、1960年代、日本でも本格的にSFの芽が育ち始めます。
1957年、星新一が、夜空に突如として煌めきだした超新星のように、処女作「セキストラ」で商業誌デビューしました。
筒井康隆も小松左京もまだ誰もいなかった世界に星新一が現れ、日本のSFの歴史が始まったのです。
そして筒井康隆の傑作、バブリング創世記の冒頭「ドンドンはドンドコの父なり。ドンドンの子ドンドコ、ドンドコドンを生み、ドンドコドン…」のように、SF界でも星新一に続き、小松左京、筒井康隆、眉村卓、豊田有恒、平井和正、横田順彌、かんべむさし、新井素子、アニメ界では手塚治虫、永井豪、石ノ森章太郎、藤子不二雄…次から次へとSFの裾野は広がり、小説に留まらずアニメや音楽の世界にまでSFは拡散し続けました。
そして筒井康隆は言いました。
「SFのSは、サイエンスのSではない。単にSFのSである」
「SFのFは、フィクションのFでも、ファンタジーのFでもない。ましてファクトのFではない。SFのFである」
「今となっては、SFの語源を探っても無駄だ。現にSFという言葉があるのだと思えばそれでいい」
科学の急速な進歩に追いつき追い越せと「科学的知識を基にした幻想的な設定で未来の世界を描く」などという小さな枠には収まりきらない過去現在未来、ミクロからマクロ、深く人間の心理の奥底まで広がり、それは純文学が陥った文学で人間を描くなどという狭いガラパゴス的世界感から文学の手法を用いて社会的、精神的、宇宙的、時間的広がりの中で人類の行く先を描くという壮大な分野に発展していきました。
それをSFの拡散と浸透の簡単な比喩を用いて表現するならば、ビッグバーン的な劇的進化ともいえます。



僕にとってSFは…
そんなSFに僕が出会うにはまだまだ先のこと。その出会いまでに、星新一はたくさんのショートショートを生み出し、更にはエッセイ集の数々を上梓しました。
大東亜戦争が終わり16年が過ぎた昭和36年夏、僕は生まれました。
フォークソングの一節にある「戦争を知らない子供たち」などという言葉さえ既に古臭く感じるほど、パーッと弾けだした世代です。
世の中は高度成長期の上り坂にあり、テレビ、冷蔵庫、洗濯機やマイカー、新幹線、月面有人着陸、大阪万博、太陽の塔、科学技術の新たな進歩により生活は右肩上がり、そして工場乱立による公害問題、人口の急激な増加等々、社会的価値観も大きく変貌し、僕らが育ってきた世の中はまさにSF社会の後追い的なバラ色と暗黒の入り交じった社会が見え隠れする時代でした。
大好きなテレビ番組を思い起こせば、古くはジャイアントロボ、大怪獣シリーズのゴジラ、大魔神。現代も色あせずに続いているウルトラマン、仮面ライダーシリーズが始まり、その傍流的ヒーローとして、ミラーマン、レインボーマン、ライオンマン、アニメではエイトマン、スーパージェッター、鉄腕アトム、マジンガーZ、サイボーグ009、デビルマン、宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999、海のトリトン、新造人間キャシャーン、パーマンやドラえもんまで今に続くSFヒーローが続々登場した時代です。
その作品の数々がその後の僕の人格形成にどれほどの影響を与え続けてくれたことか。
そして、これらヒーロー物の制作に多くの若きSF作家たちが携わっていたことを後になって知りました。
このブログでは、星新一作品を中心にその他、SF界に綺羅星のごとく散らばる作品の数々を手に、思い浮かんだことや心を動かされたことなど徒然なるままに書いていきたいと思います。

