特にSFというジャンルにおいてはその歴史の新しさもあり、みんなが自由に新たな表現すなわち実験的と言える作品を生み出しやすい土壌が培われているのか、日本のガラパゴス的小説である「私小説」などとは一線を画すSFの特徴だと思います。
厳密に言って、ここで紹介する作品が実験小説とは言えないかも知れない。でも、あまり他の作家がやらない手法ではあります。
【幻の戦士・鈴唐毛の馬慣れ】中村誠一著
収録作品集 定本ハナモゲラの研究(講談社)
昭和54年刊行
著者の中村誠一は、1947年(昭和22年)東京都生まれ。【中村誠一とは何者ぞ】
ジャズ・テナー・サクソフォーン奏者として、ジャズピアニスト山下洋輔らと共に山下洋輔トリオで活動していたことは有名です。この時期に筒井康隆とも親交を深める。
そのサクソフォーン奏者である中村誠一による畑違いの小説です。
読んでみると分かりますが、何を書いているのかさっぱり分かりません。
「定本ハナモゲラの研究」で発表されたものですから、これは言葉遊びの小説と言えます。
「ハナモゲラ」をご存じの方も今となっては少数派でしょう。
80年代、タレントのタモリらによって広められた意味の無い、でも何処か意味のありそうな言葉でおもしろおかしく会話をしたりする言葉の一連を「ハナモゲラ」と言います。
ありそうでなさそうな単語がその会話や文章にちりばめられており、ツボにはまると抱腹絶倒。
鋭い言語感覚をもって発せられた、日本語を破壊するかと思えるほどのメチャクチャな単語や文章。
言葉を破壊を題材とした実験的な小説とも言えます。
参考に筒井康隆の裏小倉
「はれすぎて なつぼけらしく うろたえの こどもほすてす かまをとぐやま」
ハナモゲラによる百人一首パロディです。
【セキストラ】星新一著
収録作品集 「人造美人」「ようこそ地球さん」
1957年(昭和32年)に同人誌「宇宙塵」に発表され、すぐさま商業誌「宝石」に転載された星新一のデビュー作です。
新聞記事をつなぎ合わせるという今までにない形式で進行する物語。
電気性処理機の普及で「世界連邦」を樹立するという発想が新しく、大下宇陀児からこんな作品があると紹介された江戸川乱歩は「これは傑作だ。日本人がこういう作品を書いているということがわたしを驚かせた。このようなアイデアで世界連邦ができあがることがとても愉快だ」と絶賛したという作品です。
黎明期の日本SF界にあっては、まだまだ手探り状態の中、星新一の登場、その作風は革新的の際に立っていたのだろう。
そのような土壌があるためか、文壇の中にあって特にSF小説は実験的な作品が多いと感じられます。それは先ほど書いた「手探り状態」が成せる技だったのかも知れません。
そして、星新一にしても筒井康隆にしても、その実験的な作品、つまり言葉を換えれば「同じ手法、同じコンセプト」の作品は絶対に書くものか、という意気込みで生涯作品を発表し続けました。それが日本SFの魅力の一つであったのかも知れません。

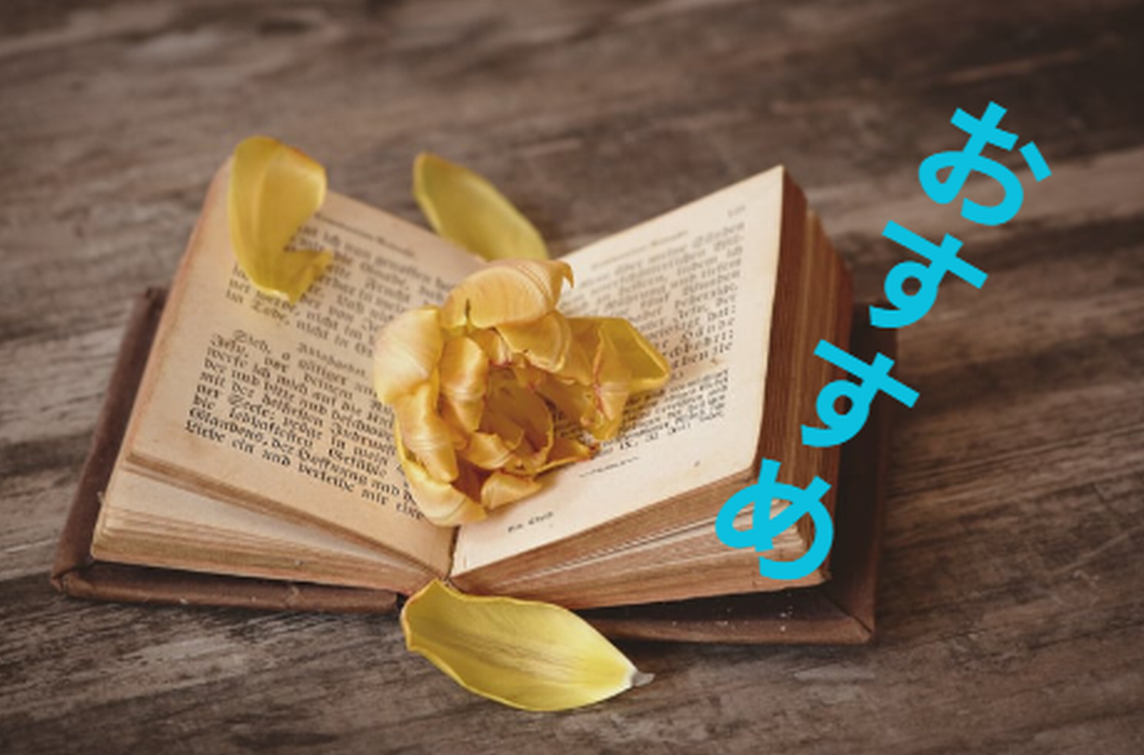
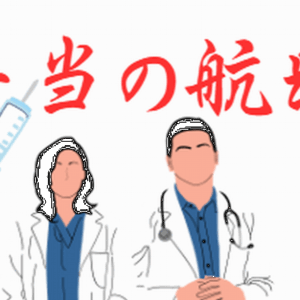

コメント