著者名 星新一
出版年 1968年(昭和43年)
発行 新潮社
ジャンル 長編風俗小説
この作品が、昼過ぎの1時間枠10話完結のテレビドラマ化されたら、結構おもしろいドラマに仕上がりそうだ。
とにかく会話のテンポがよい。上品でちょっと変わった主人公たち二人の出会いが、このユーモラスで軽快でおしゃれな会話で始まります。
「仕事で行き詰まった時に、万年筆のペン先にマニュキュアを塗って気晴らしを…」という一文があります。
この作品を電子書籍で読み直し、気づいたのですが、「…クリップにマニュキュアを塗って…」と書き換えてありました。
著者が、時代とともに分かりづらくなる言葉を、別の言葉に置き換えるなど、過去の作品に手を加え続けていた話は有名ですが、「万年筆」が将来、使われなくなることを考えて置き換えたのだろう。
でも僕は思います。「もの」は生きています。万年筆に替わりボールペンが現れ、さらには、ワープロとその姿は変わっても、100年後に万年筆がこの世からなくなるだろうか。
例えば70年代から80年代、「レコード盤」は、「カセットテープ」の身軽さ、そして好きな曲を集めて個人で楽しめるという利点が若者の間で認められ、さらには、もっと音質がよくデジタル音源として楽しめる「CD」、次には「MD」、そして「iPod」と技術革新はとどまるところを知りません。
一時は製造をやめてしまったレコードは、CDだけでアルバムを制作していたアーティストの中から、いつ頃からか、レコード盤も同時発売するようになり、今では「レコード盤」を求める音楽マニアが増えているといいます。

そこには、便利さだけではない人間ならではの天邪鬼的な指向があります。
つまり便利さから離れた、手間の掛かる、面倒くさい、でも、だからこそ味わいがあるという「趣味性」という独特の感性があります。
僕たちが求める音楽や映像の楽しみ方にはには、年齢とともに膨れ上がる「郷愁」というものも大きいのです。
万年筆もぜんぜん社会から消え失せてはいません。
手帳や日記を書く場合は「万年筆」という人は少なからずいます。
気まぐれで、天邪鬼、それが人間なんですね。
「気まぐれ指数」は昭和37年末から東京新聞に連載された星新一の長編小説。そして唯一の風俗小説です。
物語の舞台は、東京タワー(昭和33年に完成)周辺。その界隈で事件が起こります。
この作品は星新一、唯一の新聞小説であり、唯一の風俗小説という点、そして作品自体に寓話性はなくラストのドンデン返しやオチもなく、全体に流れる小春日和のような穏やかな、ユーモア溢れる作品という点で異例の作品といえます。

短編作家が長編を書くとなれば、作品の構成から雰囲気、登場人物の描き方まで全く異なるのではないかと思います。人物設定もエヌ氏やエフ氏という訳にもいかないだろう。
星新一の魅力のひとつに、風景描写があります。
年を経るに従い、ムダを削ぎ落とし風景描写等は少なくなりましたが、初期作品には魅力的描写がたくさんありました。
レイ・ブラットベリの火星年代記に触発され、小説を書きはじめたというだけあって、星新一の風景、情景描写はとても詩情にあふれて魅力的です。
そして会話が面白い。星新一独特の会話文体があります。
「○○XX…」と誰々が言った。
という説明はなく、会話文が交互に続く独特の文体です。
日本語での話し方には、老若男女職業などでそれぞれ特徴があります。
誰が話したと説明しなくても、その話し方で誰の会話かが分かるとは星新一の考えです。
黒田一郎と副島須美子との出会いの時の会話。そしてそれに続く各章での登場人物の会話の内容が面白く何故か癒されます。
あまり言われていないことですが、星新一の作品は、最後のドンデン返しだけではなく、この登場人物の会話の面白さにも「人を食った」魅力があります。知的で上品で程よくユーモラスな掛け合いです。
この種の会話の面白さは、筒井康隆や小松左京の作品にはないものです。
星新一には生まれながらの上品さが溢れています。
そして対面する2人の会話で物語が進んでいくこの作品は、そのまま戯曲として使える一面もあるようです。
言葉使いについても、登場人物の植木職人は「あっしは…」(私は…)という言葉を使っています。
これも星新一の作風としては特異なことです。
内容はSFではなくドタバタ喜劇でもなく、小春日和のような穏やかなコメディです。
些細な気まぐれで起こった犯罪が、上品に和やかに展開していきます。
会話は楽しく、ユーモアに溢れ、誰のことも傷つけません。
文庫本の末尾解説には「星新一の長編小説のおしゃべりには、やや無駄な遊びが知に溺れる傾向、自分だけが楽しんでいる気配が見られるのが欠点と言えよう。」とありますが、そうだろうか。
世の中にはユーモアを解せない人がいるというが、この解説者(奥野健男)もそのひとりなのだろう。
解説を受けるくらいだから星作品の理解者なのだろうが、この会話の良さがわからないらしい。
この「おしゃべり」、これが星新一の魅力であり、反面、日本的な陰鬱さなど微塵もないところが、文壇に評価されない一つの要因なのかもしれない。
朝一番に届く新聞の小説欄には、深刻さより、上品で知的でユーモラスな会話、NHKの朝ドラのような暖かな作品がちょうど良い。
人気作家の長編小説を読んで度々思うことは、ムダな描写が多いことです。
このページはいらない箇所だよな。読後、振り返って「やはり、枚数稼ぎ」だったなと。
そんな無駄を書く枚数的な余裕がない短編小説に慣れている僕にとっては特に強く感じるのかもしれません。
筒井康隆が実験小説「虚人たち」で、主人公が気を失った時間を白紙のページ11枚で表現したのには度肝を抜かれましたが、これは枚数稼ぎというより、また別次元の話です。
(空白のページ。本当に11ページ何も書いてなかった。空白のページで読者を笑わせることができるのは筒井康隆だけだし、こんなことが許された筒井康隆は既に大御所でした。これにはぶっ飛びました。)
「虚人たち」の空白ページのコピーです。こんなのが11ページ続くなんて…
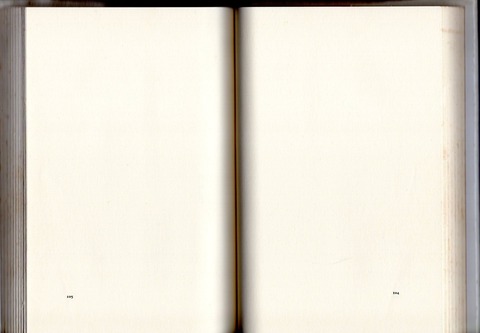
話は作品に戻ります。
物語は怒涛の最終場面。
僕の頼りない頭脳ではついて行けない複雑さですが、それでも四方八方が最終的にすべて丸く幸せに収まり、楽しく読み終えることができました。
人間の愚かさや残酷さ、身勝手さを鋭く突きつける、普段読み慣れているショートショートの手法とは真逆で、様々な状況が入り乱れた結果、みんなが見事に幸福になりました。
時にはこのような小説も良いものですね。
このように星新一にとっては異例ずくめの作品で、「書き終わったときには満足感があり、まぁ合格点、と自己採点をした…」そうですが、出版社からは、あのような作品をもう一度との依頼はなかったそうです。
本人は、風俗小説にこれ以上深く踏み込むことをせずに済んだこともあり、それで良かったのだろうと「あとがき」にありました。
単行本でこの作品を読み直したのですが、僕の手元にあるこの本は、昭和46年6刷とあり、僕がちょうど10歳、55年経過しているものです。
とある古書店で購入したもので、とても程度がよく使用感がほとんどない美品なのですが、50年の歳月を感じます。
印刷技術と年齢のせいで文字が読みづらいのは仕方がないのですが、この紙質が良くない。
光の当たる縁のあたりから徐々に茶色がかってきています。
たったの50年。西洋で使われている紙はこれほど劣化してしまいます。あと50年以上たったら読めないほどに劣化しそうです。
それに比べ「和紙」は千年以上の使用にも耐えるといいます。
日本に現存する古典はもちろん当たり前のことですが、和紙に書かれています。
古事記、日本書記、竹取物語、源氏物語、すべて和紙に写本を繰り返すことによって現代まで残されていることを思うと、今更ながらに日本の技術力の素晴らしさ、繊細さに驚かされます。
いま、世界でこの「和紙」が重要視されています。
ヨーロッパの古い文書は傷みが早く、その痛んだ古文書の修復作業に和紙が欠かせないというのです。
この気まぐれ指数にも「西欧に比べ後進国のわが国では」という会話がありますが、日本文化はもっともっと胸を張っていい素晴らしいものがたくさんあります。




コメント